コラム:イノベーション創発への挑戦
地をはう事業開発
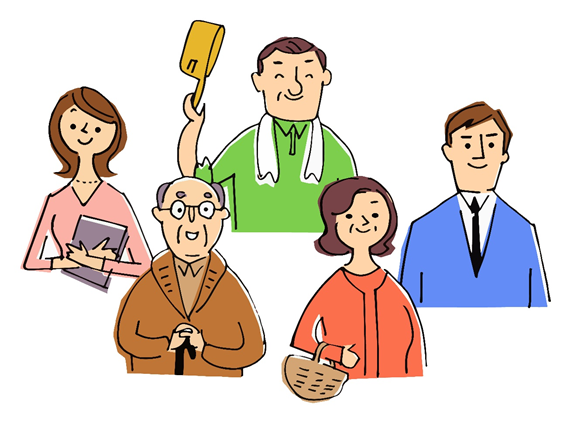
先日、「人生を振り返って反省事例はありますか?」とたずねられた時、私は「社会人最初の15年間をAI研究者、画像符号化の技術者として過ごし、技術者として長い間、地べたを這った事業開発を経験しなかったことだ」と答えた。どういうことか。
伝統的企業に入社した技術者の一生はこうだ。卒論、修論は参考程度に研究開発部門に配属され、職場で技術を教わる。10年もすれば数人の技術者グループを束ねる管理職になる。開発コストの見積もりや製品サポートで事業責任の一部を負うようになるが、製品全体の事業責任を負うことはない。そして入社20年ほどになり技術開発部門長あるいは事業部長になる機会を得る。年功序列時代の技術者の多くは 途中、企画部門か事業部門で修行しない限り、ここで初めて財務諸表に向き合うことになる。
1990年代半ばごろまでは製品の技術力を主眼に競合他社を意識して価格、機能の違いを打ち出せばよかった。今では当たり前のように使われる「ビジネスモデル」の開発経験は多くの技術者には不要だった。ビジネスモデルを表現する共通言語としてビジネスモデルキャンバス(BMC)がある。BMCは表形式の1枚シートでビジネスモデルを9つの項目に分解して説明できうる。
(1)顧客は誰か(2)顧客の課題に対して何の価値を提供するか(3)その価値をどう届けるか(4)顧客との関係をどうするか(5)どうやってもうけるか(6)自社の強みとなる資産は何か(7)価値提供のためどう動くか(8)誰と組むか(9)何にカネをかけるか――。マーケティングの軸足が顧客への提供価値に移った昨今、BMCは技術者にも必修だろう。
「空中戦の会議」という言葉をご存じだろうか。例えば独居老人向け遠隔医療の新規事業を議論する会議だとしよう。顧客は誰かという議論をしているときに、遠隔医療産業全体の傾向を述べるAさんがいる一方で、イスラエルとの遠隔医療を導入したいBさんがいる。テレビ会議での問診をCさんが主張し、それよりは巡回バスでの移動手段の確保をDさんが訴える。だが、実際誰も独居老人と会っていない。課題と価値提供の中身が違うので議論が空中ですれ違うという訳だ
BMCに沿って話せば、言語が統一されるので、まだ空中戦の会議を減らすことができるが、それでも空論になりかねない。本来であれば現場を訪ね歩き、経験し、共感する。そして(2)の「顧客の課題に対して何の価値を提供するか」の話をしたい。空中からではなく地上で議論したいのだ。
上司の指示で立案する人(高度1万メートル)、コンサルティング会社のリポートから立案する人(高度5000メートル)、マーケティングの本で得た知識からら入る人(高度3000メートル)、ヒアリング情報で空想する人(高度300メートル)、情報通の知人と会議を重ねて推論する人(高度100メートル)からは、地面を歩くユーザーの汗と息遣いは見聞きできない。地べたを這った事業開発を経験しなかった私は、今必死で取り戻そうとしている。
ドコモのイノベーション創発を牽引してきた栄藤氏による2021年3月17日の日経産業新聞「Smart Times」を翻案したものです。



 を押すとこのチャットを継続したまま画面を最小化できます。
を押すとこのチャットを継続したまま画面を最小化できます。